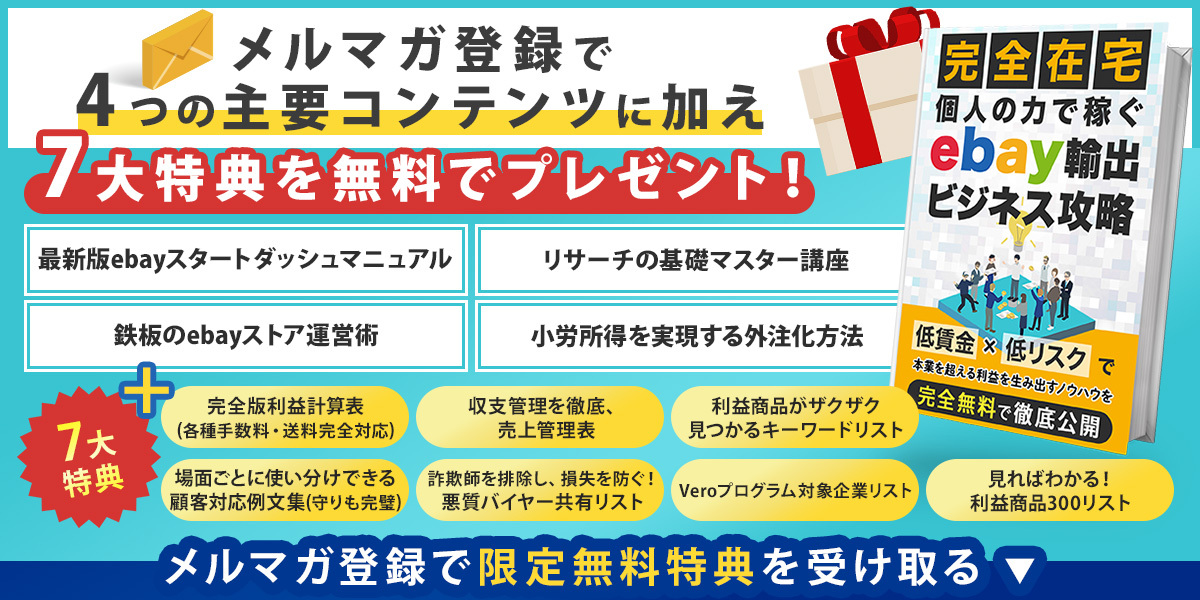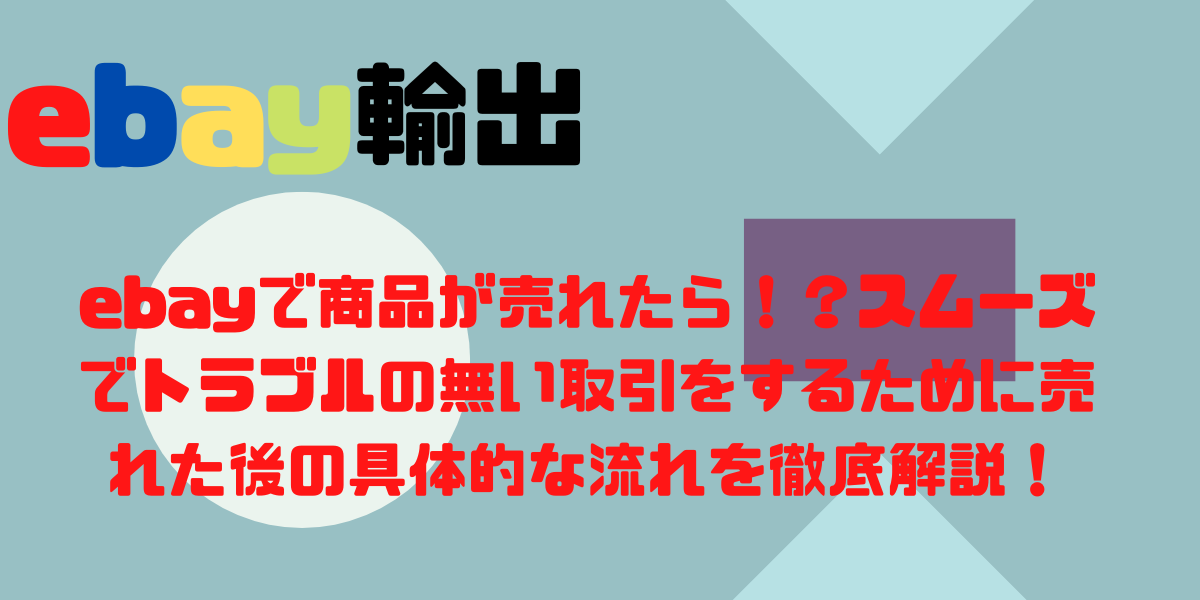こんにちは、tatsuyaです。
本日は「シュガーマンのマーケティング30の法則」の書評の続きです。
この記事でわかること(全2回)
ネットビジネスで使えるトリガー
【心理的トリガー17】帰属欲求
【心理的トリガー24】親近感
【心理的トリガー28】市場とのマッチング
前回の№1に関連してますので、№1を先に見て下さいね。
書籍の基本情報
著者:ジョセフ・シュガーマン
監訳者:佐藤昌弘
訳者:石原薫
発行者:太田宏
発行所:フォレスト出版株式会社
シュガーマンのマーケティング30の法則
【心理的トリガー17】帰属欲求
これからお話する重要な心理的トリガーを理解してもらうために、いくつかの点を指摘しておく必要がある。
まず、すでに学習したように、人は感覚レベルでものを買う。
そして、感覚的な買い物を理屈で納得しようとすることも学んだ。
しかし、ここからがちょっと違ってくる。
買い物を理屈で納得する人の中には、どんな理屈で納得したかはちゃんとわかっていても、感覚的な理由が何なのか気づいていない人が多い。
なぜベンツに乗るのか?なぜマールボロを吸うのか?
なぜ特定の物事が流行するのか?
理由は、彼らが無意識にその商品を所有する人々の仲間入りをしたいと思うからだ。
中略
ここで大事なのは「帰属欲求」という心理的トリガーだ。
ベンツのオーナーは、やはりベンツを所有する人のグループかその階級の一員として見られたいのだ。
中略
ある商品の所有者グループに属したいという「帰属欲求」は販売やマーケティングにおける最も強力な心理的トリガーの一つだ。
中略
商品、雑誌、サービス、もしくは場所でもいい。
何か一つを思い浮かべてほしい。
その商品かサービスの購買者グループ、その場所の居住者グループに属す人の心理にはどんな特徴があるだろうか。
特徴が分かったら、その人たちに対して、どんなアプローチが最適なのかもわかるようになるはずだ。
購入を検討させるきっかけもわかってくれるだろう。
商品が持っている魅力、そして、お客様が持っている傾向、その2つからヒントがつかめたとき、最も確信をついたアイディアが生まれるのだ。
中略
最後に紹介する例は、電子小物を販売する通販カタログ「ガジェッツ」を始めた時の話だ。このときは、これ以上ないほど理想的な顧客を見つけることができた。
カタログは電子小物づくしで、無料電話の番号も「1-800-GADGETS」にし、私が電子小物に傾ける愛情を綴った論説ページも作った。
さらには「ギズモロジー(機械仕掛け)博士号」の取得を証明する卒業証書まで特別に用意してみた。卒業証書には、次の2つの部類を用意し、いずれかに当てはまっていることを条件にした。
どんな部類だったのか、ご笑欄頂こう。
【第一部類】
以下のすべてに該当する方。
電気工学系卒であること。
多発計器飛行証明取得者。
現役でアマチュア無線ができること。
プロ級のアマチュアカメラマンであること。
これだけの技能と条件をすべて満たすことは比較的困難と思われますので、多少条件を緩和した第2区分を設けています。
【第2部類】
当カタログで商品を購入した方。
どの商品でも、字が読めない方でも、なんと!注文一つで資格が得られます。
2つの区分のいずれかに該当する方には、立派な証書をお送りします。
証書は額に入れて飾ってください。
あなたが厳しい基準に合格し、晴れて「ギズモロジー博士号」を取得したこと、「ギズモロジスト」として認証されたことは世界的に認められているのです。
およそ100人が、第1部類に挙げた厳しい条件を満たすとして申し出てきた。
この第1部類に挙げたものは、まさしく私自身が持っていた資格だった。
電気工学科は卒業こそしていないが、軍隊に召集されるまでの3年半、大学で電気工学を勉強した。
この1つを除けば、すべての条件を満たしていた。
多発計器飛行証明を持つ操縦士で、現役アマチュア無線家で、熱心なアマチュアカメラマンだったからだ。
単に、自分と同じような電子小物趣味を持つ人を見つけようとしただけではない。
私が電子小物への愛着を追求する中で経験した様々なことから、同じように経験してきたギズモロジストたちを見つけだそうとしたわけだ。
彼らは、確かに私と同じ部類に入る人々だったのだ。
「帰属欲求」は、なぜ特定の商品やサービスを購入するに当たって、最も強い心理的トリガーの1つだ。
お客がどんなグループに属しているかを見極め、次にお客のニーズや欲求と自分の商品との接点を見つけ出すことができれば、このトリガーを上手に使うことができるはずだ。
現在ではコミュニティー運営が流行っていますが、それと似た感覚なのかなーって思います。
人間って、やっぱり優れたコミュニティーに属したい欲求があるんだなって。
言葉を選ぶのが難しいけど、差別の逆の感覚なんでしょう。
有名人が使っているものを使いたくなる。
人に自慢できるようなもの、見栄を張ることができるようなものを購入する。
前回、感覚で人は物を買い、理屈で納得させるという話がありましたが、さらに今回の帰属欲求をあわせてみると、人間って、本当に動物だなと思う。
感覚だけで「なんか良さそう、有名人も使っているし」という理由だけで意思決定が決まっているってことだから。
セルフブランディングとあわせて、コミュニティーを運営し、その中でコミュニティー参加料を得たり、コミュニティーの中でよいと思った商品を提案して利益を出していく。
既にネットビジネスの流れはコミュニティー運営にきているのかもしれないが、今後はこのような傾向が加速していくような気がしてます。
【心理的トリガー24】親近感
私は町のエネルギーを味わいながら歩いていた。
ときどき店に立ち寄ったりしていると、突然、すぐ目の前に、取引き先のアメリカ人が歩道を歩いてくるのが見えた。
本当にびっくりした。
香港のようなまったく見知らぬ土地で知り合いに会うなんて、なんてことだ。その人とは、それまでさして親しくもなかったのに、急に親近感が湧いた。
彼を夕食に誘い、その日の晩に会う約束をした。
結局のところ、それまで以上に彼は私に商品を売るようになった。
きっと、まったく見知らぬ環境で知り合いにあったという意外性のために、相手への好感が増したのだろう。
「親近感」は広告でも同じことが起こる。
雑誌を読んだいる人が、たまたまあなたの会社のロゴや会社名に見覚えがある。
すると、そこには親近感が存在するのだ。
読み手は見知らぬ広告主達に囲まれた環境で知り合いを見つける。
あなたの会社は知らない存在ではない。
身近な存在なのだ。
中略
「親しみ」や「親近感」という心理的トリガーには、「親」という文字が使われている。
人は自分の親や家族といる時が一番居心地がいいのだ。安心感や信頼感が持てるし、隙を見せてもかまわない。
つまり、親近感を抱くと隙だらけになるのだ。
中略
私は不動産屋からしょっちゅう売り込みをかけられる。
ダイレクトメールを繰り返し送ってくるのが一番なじみ深い連中だ。
事実、自分の家を売ることになったときに選んだのは、ダイレクトメールの頻度に比例して最もなじみ深かった不動産やだった。
政治家が自分の選挙区に名前を広めるのも同じ理由による。
互いの政策に突出した違いがなければ、たいてい認知度の広さが当選する確率を高める。
「親近感」の威力を示すもう一つの例がある。
私が陸軍にいたときの経験だ。
私は、フランクフルト中流の軍諜報機関でかなり融通のきく仕事に就いていた。
私服を着用し、任務の遂行も好き勝手にできた。
ところがある日、私は大とちりをしてしまった。
一時アメリカに帰るためにドイツを離れたのだが、上官には10日間の休暇としか言っていなかった。
戻ってくると、すでに自分の籍がなかった。
必要な書類をきちんと提出しなかったため、不在中は無許可離隊とみなされてしまったのだ。
私はドイツのオーバーウルゼルという郊外の遠い町にあるキング基地の小さな軍諜報機関に左遷された。
軍服を余儀なくされ、出掛けられる場所も限られてしまった。
その後の数週間、私は司令官の目を引くためにありとあらゆる手をつくした。
司令官は基地で職務を与えられるのを待つ兵士らがよく懇願に行く相手だ。
当時の私の任務は、将校たち全員が通る持ち場の警備だった。
私は通りにある掲示板にユーモアたっぷりのニュースレターを貼った。
警備に立っている間に自分でタイプしたものだ。
すると、私のニュースレターを将校たちが朝一番に読むようになった。
毎朝笑ってくれたのだ。
当然、私は誰が書いたのか、はっきりと分かるようにしていた。
その後、将校の子供たちが通学途中に私の部隊の横を通ることに気づいた。
そこで、風船ガムの入った大箱を用意した。
子どもたちが通った時に「おいで」と手招きし、風船ガムを配りながらこう注意した。
「風船ガムをあげよう。でも、シュガーマンさんからもらったなんて誰にも言っちゃ駄目だよ。シュガーマンさんだよ。いいかい、シュガーマンさんからガムをもらったんじゃないからね」
私はガム配りを毎日続けた。
ニュースレターと風船ガム作戦を始めてしばらくしないうちに、私はもっといい仕事に就くことができた。
なぜ自分を選んだのかを聞いてみると司令官からこんな答えが返ってきた。
「このいいポジションを誰にあげようかと考えていたら、君の名前がふと頭をよぎったんだよ」
人は自分の知っている相手から物を買う傾向がある。
セールスパーソンとしては、「親近感」という心理的トリガーを認識し、お客が自分の商品やサービスを安心して買えるようにすることが重要だ。
だから、自分の名前を常にお客の目に触れさせるほうがいい。
なじみのあるブランドネーム。
何度も登場してよく知られるようになったロゴ。
誰のものだか直感的に理解されているキャッチコピー。
人々が口をそろえて言えるなじみ深いフレーズや言葉。
これらがいかに重要か理解しておくことだ。
どれも、あなたとあなたのお客を「親近感」でつなぐ接点となるのだ。
いわゆる潜在意識への「すりこみ」や単純接触効果と似たようなものなのかなって思いましたが、このエピソード凄いね。
シュガーマンさんはこれを狙ってやっていたのかと思うと、改めて凄い人だなと思う。
TwitterなんかのSNSも自分がフォローしている人のTweetは毎日みんな見ていますよね。
私もイケハヤさんをフォローしているのですが、普段から自分に刺さるまくるTweetを連発してきて、さらに、毎回あのアイコンが目に入るもんだから、つい師事してしまいそうになります。
親近感とか単純接触効果とかは、営業マンなら無意識のうちに使ってるスキルかもしれないけど、意識的にシュガーマンさんみたいな使い方ができたら面白いなって思う。
つまり、ブログ書け × YouTubeやれ × Twitterやれってことかな。
これから副業の波がくることを考えると、全部やってるだけで親近感があるよね。
やっぱり一番効果があるのはダイレクトマーケティングであるというのが心理学を学習しているとよくわかる。
【心理的トリガー28】市場とのマッチング
私がセミナーで教えていた重要な教訓の一つに、50年代に活躍した人気歌手、ボビー・ダーリンに教わったものがある。
ボビー・ダーリンがどのように有名になったかというストーリーにまつわる教訓だ。
ボビー・ダーリンは若い頃からニューヨークで歌手として活動していた。
しかし、なかなか音楽ビジネスでは、レコード会社の目にとまることさえない日々だった。
レコード会社をいくつも訪ねては、昔のポピュラーソングを自分のヴォーカルでアルバムにしてほしいと説得して回った。
彼は断られ続けた。
第1に無名の若手歌手が歌う古いポップスがヒットするとは誰も思わなかった。
第2に当時は、黒人アーティストが歌うモータウン・サウンドと呼ばれる古き良きロックンロールが流行っていたからだった。
ボビー・ダーリンは業を煮やし、ついに行動を起こした。
何を?
彼は自費アルバムを制作したのだろうか。
答えはノー。
ハズレだ。
では、レコード会社を説得して作らせたのか?
そう、アタリだ。
ただ、普通ならやらない方法をとったのだ。
彼はポップスを出すのをやめた。
当時に流行していた音楽に沿って曲を書いたに過ぎなかった。
曲のタイトルは「Splish、Splish(バシャバシャ)」。
歌詞も、「バシャバシャ、俺は風呂に入っていた。土曜の夜に・・・・」と始まっていた。
つまり自分がお風呂に入っていたときのことを歌った歌だった。
ボビーダーリンの曲は、古き良きモータウン・ロックだったため、レコード会社に簡単に売り込むことができた。
そして、彼のリードヴォーカルで録音された「Splish、Splish(バシャバシャ)」は何百万枚という大ヒットとなった。レコードを聴くと、モータウンの黒人アーティストが歌っているようにさえ聞こえた。
ダーリンは当時の流行を理解し、完全な流行に沿うものを作ったのだ。
自分が歌いたい音楽からはかけ離れていたにもかかわらず。
つまり、望みやエゴや目標は脇に置き、売れるレコードをつくるという現実的な選択をしたのだ。目的は知名度を得るためだった。
自分が本当に作りたい曲を作るためには、それが必要不可欠だったのだ。
レコードがヒットし、ミリオンセラーになってもまだ、レコード会社はボビーのポップアルバムを作ってくれそうになかった。
そこで、彼は、「Splish、Splish」の成功で儲けたお金をすべて投じ、自分でアルバムを制作した。
収録したヒット曲の中には「マック・ザ・ナイフ」という古い歌があった。
これが大当たり。
アルバムは大ヒットしたばかりでなく、
シングル盤の「マック・ザ・ナイフ」が世界中でマルチミリオンセラーになったのだ。
こうしてボビー・ダーリンは「Splish、Splish」ではなく、彼がこよなく愛したポップ・ジャズ・オールディーズで知られ続けるようになったのだ。
ボビー・ダーリンの話から学べる教訓はたくさんあるのだ。
1つは目的を達成するためには、成功しているモノ真似も大切だと言うこと。
成功した方法をお手本にして、市場に合わせることも大切なのだ。
いったん名声を築いてしまえば、人とは違う自分のやりたいことがやりやすくなる。
つまり、まずは市場のニーズに答えて必要な資金を手に入れ、それから夢を追い求める。
自分にとって必要な資金を稼いだら、何でも好きなことができるのだ。
誰も可能だと思わないことだって追求できる。
商品やサービスが市場にマッチしなければ市場は反応しない。
商品がお客にマッチするかどうかは、お客の話に耳を傾け、目を向けているかどうかという単純な問題なのだ。
天才である必要はない。
優れた目と耳と少しばかりの直感があればいいのだ。
これは本当に大事。
多くの人が言っていることかもしれないけど。
自分も今ブログを始めてちょうど3ヵ月経つけど、最初は自分の情報発信できる分野を中心に記事を書いてきた。
- 仕事
- 不動産
- 不動産鑑定
などなど
しかし、世の中の反応や、Twitter民の反応を見て、自分の今までの経験よりも、副業で実体験してきた部分を先人のブログなどを真似しながらコンテンツの量を増やす方向にシフトしてきた。
もちろん、自分の知見が役に立つ部分もあるので、これらの情報も記事にしていきたいとは考えているが、まずは収益化が先だ。
サラリーマンは基本的に自分よりやる気がないし、仕事でそれほど大きな成果を出そうとは考えない若者が多くなってきている。
逆に、プライベート重視で、仕事なんかそっちのけだ。
→仕事の記事の需要は必然的に少なくなる。
不動産や不動産鑑定自体はネット民の中ではかなりニッチな産業(リアルでは巨大な市場)であり、かつ、YMYL(Your Money,YourLife)といった人の人生に大きな影響を与える分野であることから、SEOで集客することが困難(また、SNSも適切に運用できていないため、集客は0)。
→不動産、不動産鑑定の記事の需要は必然的に少なくなる。
今後も副業やYouTubeなどを中心に副業サラリーマンの役に立つ情報を発信していきたいと考えている。
終わりに
シュガーマンのマーケティング30の法則は本当に物事の本質が書かれている書籍だと感じた。
今回2記事にわたって紹介しましたが、本当に有益な書籍です。
機会があれば是非読んでみましょう。