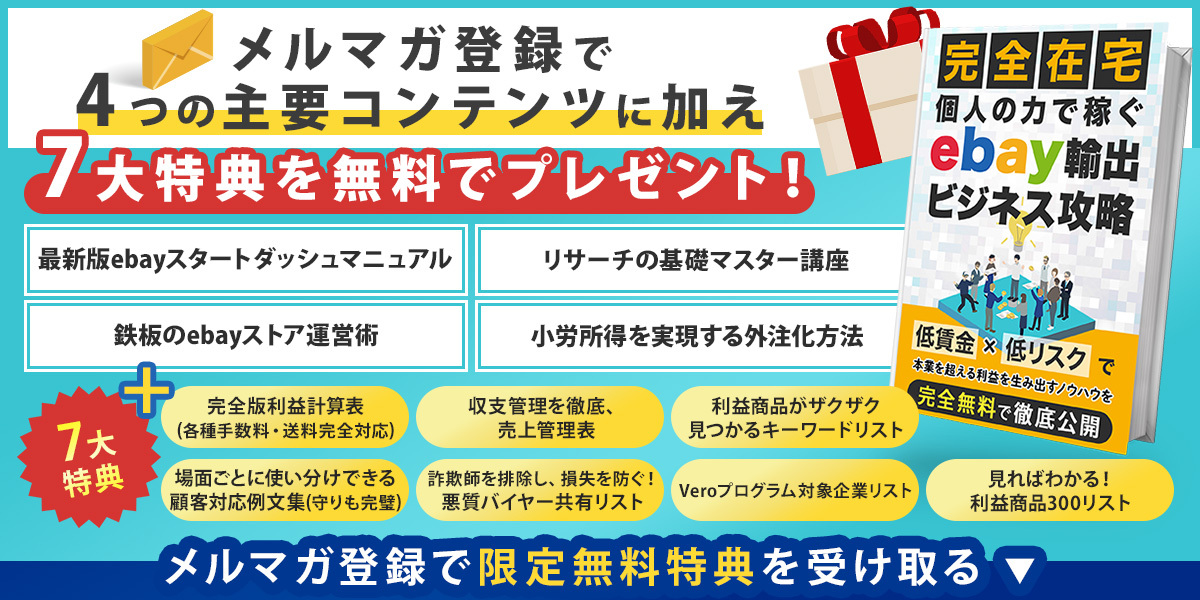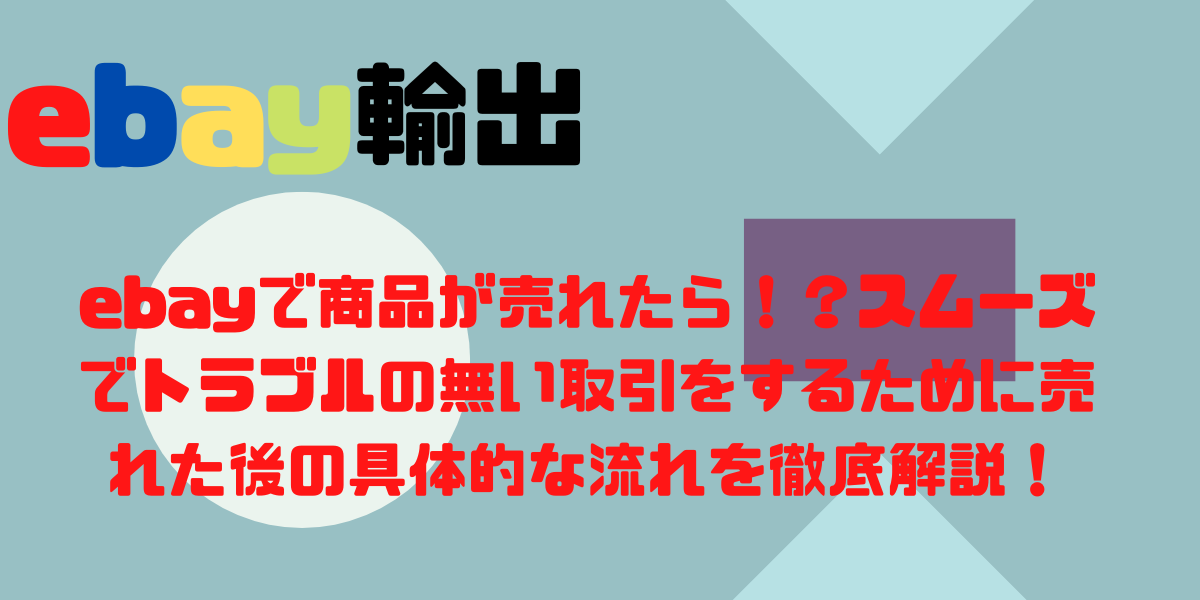こんにちは、tatsuyaです。
本日は「シュガーマンのマーケティング30の法則」の書評です。
30の「法則」とは、人が物を購入する「トリガー(きっかけ)」のことを指しています。
この30もの法則が、シュガーマンのマーケター人生の中からエピソードを踏まえて記載されていました。
今回は、その中でも、これからの時代にネットビジネスで稼ぐ人にとって重要な法則をまとめました。
特に、
【心理的トリガー17】帰属欲求
【心理的トリガー24】親近感
【心理的トリガー28】市場とのマッチング
当たりは、今後さらに重要性が高まってくると思いますので、見て頂ければ損はしないと思います。
なお、分量が多くなりそうなので、2回に分けてお届けいたします。
この記事でわかること(全2回)
ネットビジネスで使えるトリガー
【心理的トリガー8】物語(ストーリー)
【心理的トリガー11】感覚
【心理的トリガー12】理屈による正当化
【心理的トリガー17】帰属欲求
【心理的トリガー24】親近感
【心理的トリガー28】市場とのマッチング
書籍の基本情報
著者:ジョセフ・シュガーマン
監訳者:佐藤昌弘
訳者:石原薫
発行者:太田宏
発行所:フォレスト出版株式会社
シュガーマンのマーケティング30の法則
【心理的トリガー8】物語(ストーリー)
人間は物語と共に生きてきた。だからお客と心を通わせたいと思ったら、物語を使うのが一番だ。1枚の絵が千の言葉に匹敵するように、物語にも計り知れない力がある。人の心をつかみ、心と心のつながりを生む。
中略
演説家や講演家はよくスピーチの冒頭やプレゼンテーションのところどころにエピソードを挟んでいないだろうか。そういう話は面白いし退屈しない。私もつまらない話では眠くなるが、エピソード話が始まると自然と目が覚める。
物語にはたいてい教訓や先人の経験が描かれている。驚きや感動の結末が待っている場合もある。
物語の効果は販売でも同じなのだ。
セールスの中にストーリーを取り入れてみることだ。商品に関連したもの、売りやすい雰囲気を作るストーリー、お客をセールスに巻き込むストーリー。ストーリーを上手く使えば、あなたは販売効果抜群の心理的トリガーを非常に有効に活用したことになる。
人間味を感じさせるストーリーはお客の心の結びつきを作り出し、そして堅くしてくれるのだ。
中略
私が広告で成功したのも、すべてストーリーを使ってアピールしている。
そこで物語語るという手法を使った実例を私が書いた広告から1つ紹介しよう。
【見出し】視界革命
【小見出し】このサングラスをかけたとき、私は自分の目を疑った。きっとあなたも........。
【筆者署名】ジョセフ・シュガーマン
【本文】
これから話すことは実際にあった出来事です。信じるなら得をします。
信じなくても私が信じさせます。あなたのために。少し聴いてください。
友人のレンは、スグレモノを見つけるのが得意だ。
ある日、最近手に入れたというサングラスを持って喜び勇んでやって来た。
「こいつは信じられないよ。このサングラスをかけてみろよ、すごいんだ。自分の目じゃないみたいなんだ」
私は聞いた。
「何か見えるわけ?何がそんなにすごいの?」
するとレンはこう言った。
「このサングラスをかけると目が良くなるんだよ。物がはっきりくっきり、立体的に見えるんだ。気のせいなんかじゃない。君も自分の目で確かめてみろよ」
広告の続きで、私がサングラスを試したり、レンがいろいろと解説してくれるのを聞くストーリーが書かれている。会話調になっていて、直射日光や青色光の害など、サングラスについて抑えるべきポイントはすべて抑えている。
物語の効果を利用することで、読み手の好奇心をあおり、広告コピーを最後まで読ませ、そのまま最後の売り込みまで読ませるようになっている。
これが、単純な製品の紹介だったらどうだろうか。
人の耳には届かなかったと考える。
少し見ただけだと、アメリカのショッピング通販番組でありそうな展開であるが、作りこまれているのがわかるだろう。
まず、最初のつかみもベタながらうまい。
物語に引き込まれるような気がする。
また、ストーリーの中で商品の説明も十分に行うことができている。ここまで手のかかったストーリーでなくても、自分の経験と消費したものをこの例文に当て込んでいけばセールスが容易になるのではないかと感じる。
他の記事でもよくストーリーが大事とは何度も言っているが、これが具体的な例としてセールスには必須のスキルだと感じた。
ブログ記事は商品。
売り込む際にはストーリーを織り込む必要がある。
【心理的トリガー11】感覚
実際は、「感覚」について広告で覚えておくべきポイントは、たった3点しかない。もちろん人的販売にも当てはまる。
1.どんな言葉でも、それぞれにある感覚を想起させ、何らかのストーリーにする。
2.効果的なセールスは、いずれも言葉、印象、感情にあふれ、感覚に訴えかける。
3.感覚に訴えて売る。ただし理屈でその買い物を納得させる。
なぜ、アメリカでメルセデスベンツが売れるのであろうか。
ラック・アンド・ピニオン式のステアリングやABSブレーキ、そのほかの安全機能のせいであろうか?
ほかの車にも同じ機能はある。では、なぜわざわざ大枚をはたいてベンツを買うのであろう。ベンツを買う何分の1かのお金でまったくと言っていいほど同じ機能を持ったアメリカ車や日本車、場合によってはボルボだって買えるのに。
答えはこうだ。人は感覚で買い、理屈で納得(正当化)するからだ。
私がはじめてベンツを買ってそれを友人に知られてしまった時、彼らには技術的に凄いと思うところがあったから買ったのだと説明した。
しかし本当のところは、まったく技術的理由なんかではなく、感覚的に決めたのだ。
私は高級車と呼ばれるクルマを所有し、ベンツのオーナーという選ばれた人々の仲間入りをしたいだけだった。
中略
私は「感覚」という心理的トリガーを1978年に書いた電卓の広告に使った。電卓には画期的なデジタル表示機能があった。
新型ディスプレーはアルファベットと数字の両方が表示可能(この機能をアルファニューリメックという)でさらには大容量のメモリーが備わっていたため、友達の名前と電話番号を記録させることができた。
今日では大したことはないが、当時としては画期的であった。
彼らは、「アルファニューメリック」という用語をディスプレーやメモリー容量と絡めて説明しようとした。
だがその結果、広告は理屈っぽく、データだらけになった。
商品があまりに斬新で画期的であったため、理詰めでも売れると思ったのだろう。が、そうはいかなかったのだ。
私も面白半分に、類似商品をカタログ販売することにした。するとキャノンから引き合いがあった。商品を扱えば、国内での宣伝に限り、数カ月間、独占販売権をくれるという。
そこで私は、まず広告文を自分のカタログでテストしようと、「ポケット・イエローページ」という見出しと「アメリカ初のポケット・イエローページ」という見出しと、「アメリカ初のポケット・イエローページで番号選びは指先におまかせ」という小見出しを考えた。
では感覚的なコピーに耳を傾けてほしい。
「参ったなあ..........」
あなたは電話ボックスの中。電話番号が見つからない。外には人の列。プレッシャーがかかる........。
そのときだ、あなたはおもむろに電卓を取り出し、周囲の目が集中する中、ボタンをピッと押す。
するとなんと、ディスプレイに電話番号が.....。
あら不思議。これは夢?
いいや夢ではありません。
この広告は大成功だった、その後、10以上の雑誌に広告を載せ、ライバルが脱落していくのをよそに、大いに儲けることができたのだ。
感覚に訴えかける書き方をよく見てほしい。
商品の技術上の優位点やメモリー容量などには一切触れていない。
商品特性と顧客の特徴から見て、理屈では売れないが感覚に訴えかければ売れる。
それがちゃんとわかっていたのだ。
中略
当然広告では言葉の力がものをいう。
私がコピーに使った次の言葉を比べてみて欲しい。
言葉の持つ感覚的な違いがわかるはずだ。
さて、印象がいいのはどちらだろうか?
例1 モーテルのおばあさん
例2 コテージの小柄な老婦人
先日PCを新調した。
- OMEN by HP Obelisk Desktop
- (Core i9-9900K/RTX2080Ti/3TB HDD+512GB/32GB) エクストリームモデル
このようなスペックを並べられても、一般人であれば感覚的に性能の良否を理解できない。
一方、PCに詳しい人であれば、
Corei9で3TB、メモリ32GBだと!!
という評価になるかもしれない。
ただ、これだと誰にでも感覚で理解できるセールスではない。
例えばベンツの話にしてみれば、それを購入することで感覚的に「権威性」を手に入れられる、見栄を張ることができるというのが理解できる。
また、PCにしても、「4K動画の編集が容易で、作業をしながら他の処理を実行できるほどに性能が高い。また、動画をプールできる大容量のストレージを持っている。」
といったセールスのほうが、より感覚的に理解できるのだと思う。
また、言葉の使い方も大事。
同書に記載があったが、「買入」よりも「投資」と表現したほうが、すんなり入ってきやすい。
感覚に訴えかけるセールスはとても大事で、理詰めでは人の気持ちは動かせないことが多い。
このトリガーはストーリーと併せて重要なものだと感じた。
【心理的トリガー12】理屈による正当化
買い物を納得したいというニーズは、お客が無意識に感じていることが多い。口にこそ出さないが、常に感じているのだ。そのため、セールスのどこかで(通常は終わり近くで)お客が抱く無意識の疑問に答えることが不可欠なのだ。
手順としては、まず思い浮かぶ疑問について取り上げることだ。
私の広告では、必ずどこかで何らかの「納得のいく理由」を挙げ、お客の感じる抵抗感に対処していた。
「あなたにも買う権利があります」と言うだけで済むときもあれば、節約(お値打ちである理由を伝える)や健康上の理由(「目は一組しかないから、ちゃんと保護しましょう」など)、評判(「出会った男性全員がステキだと言ってくれるはず」)、高級感(「ベンツには裏地に金箔を貼ったエアーバッグが搭載されています。」)など様々な切り口を使ってお客を納得させなければならない場合もある。
中略
誰もが自分の買い物には論理的根拠があり、正当化できるものだと確信したいのだ。
私が書いた広告の中に、購買を正当化するいい例がある。
バリー社の「ファイヤーボール」というピンボールゲームに600ドルを「投資する」ことを勧める広告だ。
このコピーでは、まず他の家庭向け娯楽用品としてお買い得である理由を示した。
買い物を納得させるコピーだ。
テレビやステレオやビリヤードテーブルに600ドル以上かけた人には、ピンボールマシンをおすすめします。
テレビやステレオやビリヤードよりももっと楽しめるし、アクションも見られます。
1社に1台「ファイヤーボール」があれば、役員の娯楽用品としても、社員や従業員が休憩時間に自由に使える福利厚生としても使えます。
投資税控除、減価償却の対象にもなります。
読んでわかる通り、税額控除や減価償却に言及したことで事業者にまで経費を正当化する道を作ってあげている。
お客は買い物に納得できる理由が見つかれば、もっと気軽に買うようになるのがわかるだろう。
買いたいという衝動に反して躊躇するのはそれがいい買い物であることを保証するだけの正当な理由が不十分だからだ。
お客の抵抗感を解消するためには、感覚的に行った購買決定を論理的な理由で正当化できることを、何らかの方法で革新させることが必要だ。
そうしなければ、最後の詰めに必要な大事な「理屈による正当化」という心理的トリガーがないままになってしまう。
うーん、これは例えば女の子とワンナイトした時に
「昨日は結構酔っぱらってて、理性がない状態だったから仕方ないよ」とか
終電を逃したから、女の子とをとめてワンナイトした時に
「終電がなかったからしょうがないよ」って感じで後付で理屈をつけて納得させる感覚かなーと。
人間って自分が悪いことをしても、無駄遣いをしてしまったとしても常に自己肯定していきたい生き物なんだなって改めてこのトリガーを考えて思いました。
続く。
-

シュガーマンのマーケティング30の法則【書評】№2
続きを見る